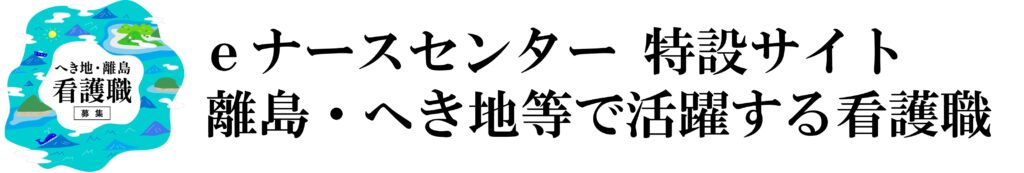秋田県の人口は、884,877人(令和7年4月1日現在)です。高齢化率は39.0%(令和6年高齢者白書)で全国1位を走り続けています。2050年には49.9%と人口の約半数が高齢者となり医療需要が更に高まることが予測されます。
秋田は、13の市、9つの町、3つの村があり、県南・県央・県北と恒常的にの3つの地区に分けています。いずれの地区も看護師不足が続いています。比較的、充足されているとされる秋田市でも介護福祉施設や診療所では恒常的に求人募集をしています。
令和6年、7年と2年継続して「あきた応援ナース」を実施しています。秋田県においては看護職の確保・定着が困難となっており、地域偏在も顕著です。そこで、看護師が不足している医療機関や介護施設を募集し、短期間就労する仕組みを考えました。看護師経験があり、1カ月以上応援施設で就業できる看護職を募集しています。詳細は「秋田県看護協会HPナースセンターあきた応援ナース」でご確認ください。登録施設などを掲載しています。

秋田県は、東北地方の日本海側に位置しています。
北京やニューヨークとほぼ同じ緯度(北緯40度)です。
●持ち家率全国1位
●全国学力・学習状況調査 平均正答率が全国トップクラス
●風力・地熱発電導入量がトップクラス 
●秋田の日本酒
良質な水とお米、冬の厳しい寒さと伝統の技が生み出すコクのあるお酒は、数え切れないほどさまざまな銘柄があり、秋田県は全国でも有名な酒どころです。
●きりたんぽ
秋田県を代表する特産品「きりたんぽ鍋」。きりたんぽは、硬めに炊た新米をすり鉢で粘りが出るまでこね、杉の棒にちくわのように巻き付け焼き、棒から外して食べやすく切ったものです。
●稲庭うどん
日本の3大うどんともいわれるています。300年を超える手作りの技による細くて平な麺で、ツルツルッとなめらかでコシのある舌ざわりは抜群のおいしさです。
●がっこ
秋田県の方言では、漬け物のことを「がっこ」といいます。がっこの種類はたくさんあり、大根、なすなど四季折々の自然のめぐみを、こうじ、しょうゆ、塩などさまざまな方法で漬け込こみます。
●秋田銀線細工(あきたぎんせんざいく)
金銀銅など、豊富な鉱山資源に恵まれていた秋田では、江戸時から金銀を利用した細工が発達しました。0.2ミリメートルほどの細い銀線をより合わせ、簡単な道具と職人の指先だけで丁寧に形を整ていく繊細な技により、ブローチやペンダントなどが作られています。
●大館まげわっぱ
「大館曲まげわっぱ」は、木こりが杉の木を曲まげ、桜の皮でぬい止めて作つくった手作りの弁当箱が始まりと言われています。江戸時代には、武士の内職として作られました。杉ならではの明るい色合いと美くしい木目が魅力です。
●川連漆器(かわつらしっき)
800年を超える歴史がある「川連漆器」は、30種類に及ぶ長い作業を経てようやく完成します。丁寧に作られた塗りの丈夫さは、多くの人に認められています。
●樺細工(かばざいく)
「樺細工」は、山桜の皮をはいで木工品の表面に貼り付つけた工芸品です。この技術は、仙北市し角館町に約200年以上前まえから伝えられています。山桜の皮の持つ美しい光沢が特長で、茶筒や手紙を入れる箱などさまざまな商品があります。
秋田県ナースセンターは秋や県看護協会が秋田県の委託事業として運営しています。主な事業内容は、看護職、看護補助者の無料職業紹介、離職時の届出制度の周知・啓発、求職相談、求人相談、求人施設の紹介、看護職の就業状況に関する調査、ナースセンターニュース(季刊誌)の発行です。
再就業に必要な基本的な知識を習得し、看護実践力と自信を高める目的で、復職支援実技研修を県央・県北・県南の各地域で14回実施。講師は、各地域の認定看護師に依頼し、地元開催による参加しやすい環境を提供しています。 今年度力を入れているのは「給付型実践型就業マッチング研修」で、求職者が興味のある求人施設で2日程度体験実習を行い、終了後に実習記録を提出することで給付金が支払われます。これにより就業後の「こんなはずではなかった」がなくなり、イメージ通りであれば就業につながります。他には、LINEによる情報発信や、復職を考える方の交流会、復職支援eラーニング研修、セカンドキャリア研修(看護職のためのセカンドキャリアセミナー、プラチナナースCafé)、採血実技演習、地域応援看護職「あきた応援ナース」など、さまざまな企画で再就業を支援しています。
これまで月1~2回、県内8カ所のハローワークで相談員による「看護のお仕事移動相談会」を実施しています。今年度は年度始めの2か月間で県内全ハローワークに出向き「看護職向け就職支援セミナー」を実施しました。ナースセンターの活動・役割・活用方法を広く認知してもらう啓蒙活動も行いました。